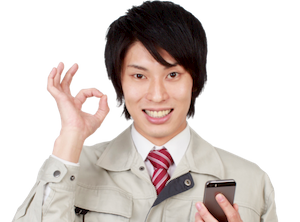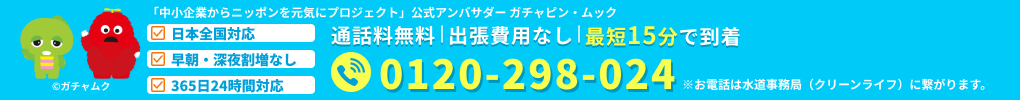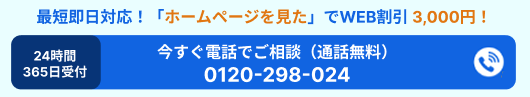寒い冬の朝、シャワーを浴びようとしたのに「お湯が出ない!」という経験はありませんか?特に厳しい寒さが続く冬場は、給湯器や配管が凍結してお湯が出なくなるトラブルが多発します。朝の忙しい時間に冷水しか出ないと、一日の始まりから大きなストレスになってしまいますね。
給湯器の凍結は、気温がマイナス4℃以下になると発生しやすく、特に北海道や東北、日本海側の寒冷地では頻繁に起こる問題です。しかし最近では、普段あまり雪が降らない地域でも、急な寒波によって給湯器が凍結するケースが増えています。
この記事では、給湯器が凍結してお湯が出なくなった場合の具体的な対処法から、そもそもなぜ凍結するのか、そして凍結を予防するための効果的な方法まで詳しく解説します。冬の水回りトラブルに備えて、ぜひ参考にしてください。
目次
お急ぎの方は
お電話ください!

0120-298-024

通話料無料 24時間365日対応
※水道事務局(クリーンライフ)に繋がります
給湯器の凍結でお困りなら お電話一本ですぐにお伺いします!
通話料無料 24時間365日対応
0120-298-024
※水道事務局(クリーンライフ)に繋がります
給湯器の凍結でお困りなら
お電話一本ですぐにお伺いします!
お見積もり 出張費 深夜割増 = 0円
「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」
公式アンバサダー ガチャピン・ムック
 ©︎ガチャムク
©︎ガチャムク
給湯器が凍結してお湯が出ないときの対処法
給湯器が凍結してお湯が出なくなった場合、焦らずに適切な対処をすることが重要です。ここでは、自分でできる効果的な解凍方法をいくつか紹介します。
- 1、気温が上がるのを待って自然解凍させる
- 2、給水バルブにタオルをかぶせてお湯で温める
- 3、ホットタオルやヘアドライヤーで解凍する
- 4、給湯器のリモコンをオフにして水を出す
それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。凍結の程度や状況に応じて、最適な方法を選んでください。
気温が上がるのを待って自然解凍させる
給湯器の凍結に気づいたときの最も安全な対処法は、気温の上昇とともに自然に解凍されるのを待つことです。多くの場合、日中になって気温が上がれば、凍結した配管や給湯器内部の氷は自然に溶けていきます。
この方法は特別な道具や技術が不要で、配管や給湯器を傷める心配がありません。凍結が軽度の場合は、午前中から昼過ぎにかけて気温が上昇すれば、自然に解凍されることが多いです。特に太陽が当たる場所にある給湯器や配管は、太陽熱の助けもあって比較的早く解凍します。
ただし、この方法は時間がかかるというデメリットがあります。朝シャワーを浴びたい時や、急いでお湯を使いたい場合には向きません。また、気温がマイナスのまま一日中推移する真冬の寒冷地では、自然解凍を期待するのは難しいでしょう。
さらに、凍結した状態が長時間続くと、氷の膨張によって配管や給湯器内部の部品が破損するリスクが高まります。そのため、長時間待てない場合や、厳しい寒さが続く地域では、次に紹介する積極的な解凍方法を試してみるとよいでしょう。
なお、自然解凍を待つ間も、定期的に蛇口をチェックして水やお湯が出るようになったかを確認してください。解凍されたら、まずは少量の水を出して配管内に残った氷が完全に溶けているか確認することが大切です。
給水バルブにタオルをかぶせてお湯で温める
凍結した給湯器を早く解凍したい場合は、給水バルブや凍結した配管にタオルをかぶせてお湯をかける方法が効果的です。特に凍結箇所が明確に分かっている場合におすすめの方法です。
まず、タオルや布を用意し、凍結していると思われる配管や給水バルブに巻き付けます。次に、別の容器でお湯を沸かし(60~70℃程度)、そのお湯をタオルにゆっくりとかけていきます。お湯の温度は熱すぎると配管を傷める可能性があるので、手で触れられる程度の温度が適切です。
タオルが冷めてきたら、再度温かいお湯をかけ、これを繰り返します。凍結が軽度であれば、10~15分程度で解凍できることが多いですが、凍結の状態によってはさらに時間がかかることもあります。
この方法のメリットは、比較的短時間で効果が現れる点です。また、特別な道具も必要なく、家庭にあるものですぐに実践できます。特に給湯器の給水部分(水が入ってくる配管)が凍結している場合に効果的です。
ただし、注意点もいくつかあります。まず、沸騰したお湯を直接配管にかけるのは避けてください。熱すぎるお湯は樹脂製の配管を変形させたり、接続部を緩めたりする原因になります。また、電気部品がある場所には水がかからないよう注意しましょう。給湯器本体に直接お湯をかけるのは危険なので避けてください。
この方法で解凍を試みる際も、無理な力を加えたり、配管を叩いたりしないよう注意が必要です。氷で膨張した状態の配管に衝撃を与えると、亀裂や破損の原因になることがあります。
ホットタオルやヘアドライヤーで解凍する
給湯器や配管の凍結部分が比較的小さな範囲で、明確に場所が特定できる場合は、ホットタオルやヘアドライヤーを使った解凍方法も効果的です。特に、給湯器本体よりも接続されている配管部分が凍結していることが多いため、そこを集中的に温めることができます。
ホットタオルを使う場合は、まずタオルを熱いお湯で濡らし、軽く絞ってから凍結している部分に巻き付けます。タオルが冷めてきたら、再度熱いお湯で温め直す作業を繰り返します。温かいタオルの熱が徐々に配管に伝わり、内部の氷を溶かしていきます。
ヘアドライヤーを使用する場合は、温風を凍結部分に当て、少しずつ温めていきます。この方法のメリットは、タオルよりも継続的に熱を供給できる点です。ただし、以下の注意点に気をつけましょう。
まず、ヘアドライヤーと水の組み合わせは感電の危険があるため、周囲に水滴がある場合は十分に拭き取ってから使用してください。また、ヘアドライヤーを長時間使用すると過熱する可能性があるため、適宜休ませながら使うことも大切です。
温度が低すぎると効果が薄く、高すぎると配管を傷める可能性があるため、中温~高温の設定で使用し、一箇所に長時間当て続けるのではなく、少しずつ移動させながら温めるのがコツです。特に樹脂製の配管は熱に弱いので、温度管理に注意してください。
解凍作業中は、定期的に蛇口を開けて水やお湯が出るようになったかチェックしましょう。水が出始めたら、少量の水を流し続けることで、残りの氷も徐々に溶けていきます。完全に解凍されるまで、根気よく続けることが大切です。
給湯器のリモコンをオフにして水を出す
給湯器内部の熱交換器や配管が凍結している場合は、給湯器のリモコンの電源をオフにしてから水を出す方法が効果的なことがあります。この方法は、特に給湯器自体の凍結が軽度の場合に試してみる価値があります。
まず、給湯器のリモコンの電源をオフにします。これにより、給湯器が作動せず、水だけが配管を通るようになります。次に、お湯を使用する蛇口(キッチンシンクやお風呂場など)をお湯側に設定して開けます。
この状態では水しか出ませんが、水の流れによって配管内の氷が少しずつ溶けていく効果が期待できます。特に、家の中を通る配管部分が凍結している場合は、室内の暖かい空気と水の流れの相乗効果で解凍が進むことがあります。
水が少しでも出るようであれば、その状態で10~15分程度水を流し続けてみましょう。徐々に水の出が良くなってきたら、凍結が解けつつある証拠です。水の出が安定してきたら、給湯器のリモコンをオンに戻し、お湯が正常に出るか確認します。
ただし、この方法にはいくつか注意点があります。まず、完全に凍結して水もまったく出ない場合は効果がありません。また、水を長時間流し続けることになるため、水道料金が気になる方には向かないかもしれません。
さらに、給湯器内部の重要な部品が凍結によって破損している場合は、この方法を試しても根本的な解決にはならないことがあります。水漏れなどの異常が見られる場合は、すぐに水道修理業者に相談することをおすすめします。
給湯器が凍結したときの症状
給湯器が凍結すると、いくつかの特徴的な症状が現れます。早期に症状を認識することで、適切な対処が可能になります。ここでは、主な症状について解説します。
- 1、お湯が出なくなる
- 2、配管や部品が破損する
これらの症状を理解し、どのような状態なのかを適切に判断することが重要です。
お湯が出なくなる
給湯器が凍結した場合の最も明確な症状は、蛇口からお湯が出なくなることです。朝起きて蛇口をひねっても冷たい水しか出ない、あるいは水もお湯も全く出ないといった状態になります。
特に寒い冬の朝に多く見られるこの症状は、給湯器内部や接続配管の水が凍って氷になり、水の流れを塞いでしまうことで発生します。凍結の程度によって症状の現れ方も異なります。軽度の凍結では、お湯の出が悪くなる、水圧が弱くなるといった前兆が見られることもあります。
また、凍結が発生すると、給湯器のリモコンにエラーコードが表示されることがあります。一般的なエラーコードとしては、「凍結エラー」や「水流異常」「点火エラー」などがあります。製品によってエラーコードは異なるため、取扱説明書を確認すると良いでしょう。
さらに、給湯器から異音がする場合もあります。これは内部の水が凍結して膨張し、部品や配管を圧迫することで発生します。カチカチ、ピキピキといった音が聞こえたら、凍結の可能性を疑ってください。
凍結の症状は、使用していない時間が長いほど悪化する傾向があります。例えば、朝一番でお湯が出ない場合は、夜間の気温低下によって徐々に凍結が進行した可能性が高いです。また、長期不在で給湯器を使っていなかった家に戻ると、凍結していることが多いので注意が必要です。
お湯が出ない症状が現れたら、まずは外気温を確認し、凍結の可能性を考慮した対処を行うことが重要です。特に気温がマイナス4℃以下になった夜の翌朝は、凍結を疑ってみるとよいでしょう。
配管や部品が破損する
給湯器の凍結がさらに進行すると、配管や内部部品の破損という深刻な症状が現れることがあります。これは、水が凍ると体積が約1.1倍に膨張するという性質によるものです。この膨張圧力は非常に強力で、金属製の配管さえも破裂させる力を持っています。
破損の初期症状としては、微細な亀裂からの水漏れが挙げられます。給湯器の周囲や配管の接続部分に水滴や湿りが見られる場合は、凍結による破損が疑われます。この段階ではまだ小さな漏れかもしれませんが、放置すると徐々に悪化し、最終的には大きな水漏れに発展する可能性があります。
また、凍結が解けた後にお湯を使用すると、給湯器内部や配管からの水漏れが明らかになることが多いです。床が濡れている、給湯器の下に水たまりができている、壁から水が染み出しているといった現象が見られたら、凍結による破損を疑う必要があります。
さらに深刻な破損では、給湯器が正常に機能しなくなります。例えば、点火はするものの温度が上がらない、異常な音や振動が発生する、ガス消費量が急に増えるといった症状が現れることがあります。これらは熱交換器や制御バルブなどの重要部品が破損している可能性を示しています。
破損の程度によっては、修理ではなく給湯器本体の交換が必要になるケースもあります。特に築年数が古い給湯器の場合、凍結破損を機に新しい機種への買い替えを検討するタイミングかもしれません。
破損が疑われる場合は、自己判断での修理は避け、専門の修理業者に診断してもらうことをおすすめします。適切な修理や部品交換を行わずに使用を続けると、更なる損傷やガス漏れなどの危険な状況につながる可能性があります。
お湯が出ない原因が凍結かどうかを見分ける方法
お湯が出ないとき、それが凍結によるものなのか、それとも他の原因なのかを見分けることが重要です。ここでは、凍結かどうかを判断するための方法を紹介します。
- 1、蛇口からお湯や水が出るか確認する
- 2、給湯器のリモコンのエラーを確認する
これらのチェックポイントを確認することで、適切な対処につなげることができます。
蛇口からお湯や水が出るか確認する
お湯が出ない状況が凍結によるものかどうかを判断するには、まず複数の蛇口で状況を確認することが重要です。家のさまざまな場所(キッチン、洗面所、お風呂場など)の蛇口をチェックして、症状の出方に違いがあるかを確認しましょう。
まず、お湯側だけでなく水側も確認してください。もし水もお湯も全く出ない場合は、給湯器の問題だけでなく、水道本管や給水管全体の凍結、または断水の可能性も考えられます。一方、水は出るがお湯だけが出ない場合は、給湯器とそれに接続する配管の凍結の可能性が高くなります。
また、家の中の場所によって症状に違いがある場合もあります。例えば、北側の部屋の蛇口は水が出ないが、南側の部屋では出るといった場合は、寒さにさらされている特定の配管だけが凍結している可能性があります。このように、どの場所でどのような症状が出ているかを詳しく確認することで、凍結箇所を特定する手がかりになります。
さらに、水の出方にも注目してください。水が少しずつしか出ない、出たり止まったりする、水圧が著しく低いといった症状は、配管内が部分的に凍結していることを示している可能性があります。完全に詰まっていなくても、氷によって水の通り道が狭くなっているケースです。
時間帯や気温との関係も重要な手がかりです。特に厳寒期の朝方(最も気温が下がる時間帯)にお湯が出なくなり、日中に気温が上がると復旧するというパターンは、凍結の典型的な特徴です。
これらの確認を通じて、症状が凍結によるものであれば、次は凍結箇所や程度を見極め、適切な解凍方法を選択することが大切です。
給湯器のリモコンのエラーを確認する
お湯が出ない原因が凍結かどうかを判断するもう一つの方法は、給湯器のリモコンに表示されるエラーコードを確認することです。現代の給湯器のほとんどは、何らかの問題が発生するとリモコン画面にエラーコードを表示する機能を備えています。
凍結に関連するエラーコードは、メーカーや機種によって異なりますが、一般的には「凍結防止エラー」「流水エラー」「点火エラー」「給水異常」などの表示が出ることが多いです。お使いの給湯器の取扱説明書には、エラーコードとその意味についての説明があるはずですので、確認してみましょう。
例えば、リンナイの給湯器では「11」「12」といったエラーコードが点火不良を示し、これは凍結が原因で発生することがあります。ノーリツの場合は「16」「50」「90」などのコードが凍結関連のエラーである可能性があります。
また、リモコン画面に「凍結防止運転中」といった表示が出ている場合は、給湯器が自動的に凍結防止機能を働かせている状態です。これは給湯器自体が凍結を検知し、内部のヒーターを作動させているか、微量の水を循環させて凍結を防いでいることを意味します。
リモコンに表示がない、または電源が入らない場合は、凍結によって給湯器の電源系統や制御基板が影響を受けている可能性もあります。特に、給湯器の設置場所が屋外で厳しい寒さにさらされている場合は、こうした深刻な凍結被害が生じることがあります。
リモコンのエラー表示と合わせて、気温の状況や水の出方なども総合的に判断することで、より正確に凍結の有無を確認することができます。不明な点があれば、給湯器のメーカーのお客様センターや専門の修理業者に問い合わせることをおすすめします。
給湯器が凍結する条件・原因
給湯器が凍結する背景には、特定の条件や原因があります。これらを理解することで、効果的な予防策を講じることができます。
- 1、お湯用の蛇口を長い期間使っていないとき
- 2、気温がマイナス4℃以下になるとき
これらの条件について、詳しく見ていきましょう。
お湯用の蛇口を長い期間使っていないとき
給湯器が凍結するリスクが高まる条件の一つは、長期間にわたってお湯を使用していない状況です。お湯を使わないと配管内の水が滞留し、外気温が下がった際に凍結しやすくなります。
特に注意が必要なのは、冬季の旅行や出張などで家を空ける場合です。通常の生活では毎日お湯を使うことで、配管内の水が定期的に入れ替わり、比較的温かい新しい水が供給されるため、凍結のリスクが低くなります。しかし、数日間家を空けると、配管内の水は動かないまま外気温の影響をまともに受けることになります。
また、普段あまり使用しない場所の給湯設備も要注意です。例えば、来客用の浴室や、季節によって使用頻度が変わる屋外のシャワーなどは、長期間使われないことで凍結リスクが高まります。こうした場所は定期的に少量のお湯を出すなどの対策が必要です。
さらに、住宅の一部だけを使用している場合も注意が必要です。例えば、2階建ての家で冬季は1階だけで生活し、2階のお湯をほとんど使わないといった状況では、使用していない階の配管が凍結するリスクが高まります。
凍結予防機能がついている近年の給湯器でも、長期不在の場合は注意が必要です。自動凍結防止機能は電気を使って作動するため、電源が切れていたり、停電が発生したりすると機能しません。長期間家を空ける場合は、後述する「水抜き作業」を行うなどの対策を取ることをおすすめします。
凍結のリスクを減らすためには、長期不在時にも定期的にお湯を使用できるよう、信頼できる人に依頼するか、自動で少量の水を流す装置を設置するなどの対策を検討するとよいでしょう。
気温がマイナス4℃以下になるとき
給湯器が凍結するもう一つの重要な条件は外気温の低下です。一般的に、気温がマイナス4℃以下になると給湯器や配管の凍結リスクが高まります。特に夜間から早朝にかけての気温低下は注意が必要です。
気温の低下は地域によって大きく異なります。北海道や東北などの寒冷地では、冬季のマイナス10℃以下の気温は珍しくなく、凍結対策が生活の一部として定着しています。一方、関東以西の温暖な地域でも、近年は記録的な寒波に見舞われることがあり、普段は凍結を経験しない地域でも対策が必要になるケースが増えています。
また、同じ地域内でも、建物の立地条件によって凍結リスクは異なります。北向きの場所や日陰になる場所、風当たりの強い場所は特に冷え込みやすく、凍結のリスクが高まります。このような場所に給湯器や配管が設置されている場合は、より念入りな凍結対策が必要です。
気温だけでなく、風の強さも凍結に影響します。風速が強いと体感温度が下がる「風冷効果」が生じ、実際の気温以上に配管が冷やされることがあります。特に強風を伴う寒波の際は、マイナス4℃より高い気温でも凍結することがあるので注意が必要です。
気象予報で「凍結注意報」や「低温注意報」が出ている場合は、給湯器の凍結対策を講じるタイミングです。前日の夜に対策を行っておくことで、朝になって水が出ないという事態を防ぐことができます。
また、気温の変化だけでなく、急激な温度変化にも注意が必要です。比較的暖かい日が続いた後で急に冷え込むと、凍結対策を怠りがちになるため、思わぬトラブルに見舞われることがあります。季節の変わり目や、天気予報で大幅な気温低下が予測される場合は特に注意しましょう。
給湯器が凍結してお湯が出なくなるのを予防する方法
給湯器の凍結は、適切な予防策を講じることで防ぐことができます。ここでは、効果的な凍結予防方法を紹介します。
- 1、給水管を保温する
- 2、専用の凍結防止剤を使用する
- 3、凍結予防ヒーターを活用する
- 4、給湯器・お風呂で水抜き作業をする
これらの方法を適切に組み合わせることで、冬場の給湯器トラブルを効果的に予防できます。
給水管を保温する
給湯器や配管の凍結を防ぐ最も基本的な方法は、給水管を適切に保温することです。特に屋外に露出している配管や、北側の日当たりが悪い場所にある配管は、保温材で包むことが重要です。
保温材には様々な種類がありますが、一般的には発泡ポリエチレン製の保温チューブが手軽で効果的です。これはホームセンターなどで簡単に購入できて、自分で取り付けることができます。保温チューブは配管の直径に合ったサイズを選び、隙間なく覆うことがポイントです。
保温チューブを取り付ける際は、まず配管が乾いた状態であることを確認し、チューブを切れ目に沿って開いて配管に被せます。チューブ同士の継ぎ目や端部は、専用のテープでしっかりと密閉することが大切です。隙間があると、そこから冷気が入り込み、効果が半減してしまいます。
より高い保温効果を得るためには、保温チューブの上から断熱テープを巻いたり、複数層の保温材を使用したりする方法もあります。特に寒冷地では、単層の保温材だけでは不十分な場合もあるため、二重、三重の対策を検討しましょう。
また、保温材だけでなく、配管を収納するボックスを設置する方法も効果的です。市販の配管カバーボックスや、簡易的には発泡スチロールの箱で包むことでも、外気からの冷気を遮断する効果があります。
保温対策を行う際は、給湯器本体だけでなく、接続されている給水管全体を確認することが重要です。特に建物の外壁を通過する部分や、地面に近い部分は凍結しやすいので重点的に保温します。また、経年劣化により保温材が破れたり剥がれたりしていないか、定期的に点検するのも忘れないようにしましょう。
専用の凍結防止剤を使用する
配管内の水の凍結点を下げる方法として、専用の凍結防止剤を使用する方法があります。これは特に寒冷地や、保温材だけでは対策が難しい場所に効果的です。
凍結防止剤は、プロピレングリコールや食品添加物として認可されている成分を使用した安全なものが市販されています。これらは水に混ぜることで凍結点を下げる効果があり、通常の水が0℃で凍るのに対し、防止剤入りの水はマイナス数度でも凍らないようになります。
使用方法は製品によって異なりますが、一般的には水道の元栓を閉め、給湯器や配管内の水を抜いた後、指定の濃度に薄めた凍結防止剤を注入します。特に長期間家を空ける場合や、使用頻度の低い別荘などでは効果的な対策となります。
ただし、凍結防止剤を使用する際は以下の点に注意が必要です。まず、飲用水として使用する水道に入れることは避けるべきです。たとえ安全性の高い成分であっても、飲用を目的としたものではないため、使用するのは給湯器の循環系統や、飲用に使わない配管に限定します。
また、防止剤の効果は永続的ではなく、時間の経過とともに徐々に薄まっていくため、定期的に濃度チェックや追加投入が必要です。使用期間や交換時期は製品の説明書に従いましょう。
さらに、防止剤の使用は配管の材質によって制限がある場合もあります。特に古い配管や特殊な材質の配管では、防止剤の成分が影響を与える可能性があるため、事前に適合性を確認することが大切です。
凍結防止剤は単独で使用するより、保温材との併用がより効果的です。外部からの冷気を遮断しつつ、万が一冷え込んだ場合にも凍結しにくくする二重の対策として利用するとよいでしょう。
凍結予防ヒーターを活用する
特に寒冷地や厳しい冬を迎える地域では、電気式の凍結予防ヒーターの設置が効果的です。これは配管に巻き付けるタイプや、給湯器に内蔵されているタイプがあり、電気の熱で配管を温めて凍結を防ぎます。
配管用の凍結予防ヒーターは、長さ調節可能なテープ状やコード状のものが一般的です。使用方法は、まず配管の表面をきれいに清掃した後、ヒーターを配管に沿って巻き付けていきます。その上から保温材で覆うことで、熱が逃げにくくなり、効率的に配管を温めることができます。
多くの凍結予防ヒーターには自動温度調節機能が付いており、外気温が下がると自動的に作動し、温度が上がると停止します。これにより、必要なときだけヒーターが働き、電気代の節約にもつながります。
また、最近の給湯器は本体に凍結予防ヒーターが内蔵されているものが多くあります。これらは電源を入れておくだけで自動的に凍結防止機能が働きます。ただし、電源が切れていると機能しないため、コンセントが抜けていないか、ブレーカーが落ちていないかを確認することが重要です。
凍結予防ヒーターを使用する際の注意点としては、まず電気代がかかることが挙げられます。特に広範囲の配管を保護する場合や、厳寒期が長く続く地域では、電気代の負担が無視できない場合もあります。省エネタイプを選んだり、必要な箇所に絞って設置したりするなどの工夫が必要です。
また、ヒーターの性能を最大限に発揮するためには、適切な設置と定期的な点検が不可欠です。ヒーターが配管に密着していなかったり、破損していたりすると、効果が大幅に低下します。冬季の前には動作確認を行い、異常がないことを確認しましょう。
長期間家を空ける場合でも、凍結予防ヒーターは電源を入れたままにしておくことで機能します。ただし、長期不在時には水抜き作業と併用するなど、複数の対策を講じることがより安心です。
給湯器・お風呂で水抜き作業をする
長期間家を留守にする場合や、特に厳しい寒さが予想される場合は、給湯器やお風呂の配管内の水を抜く水抜き作業が最も確実な凍結予防法です。配管内に水がなければ凍結の心配はありません。
水抜き作業の基本的な手順は以下の通りです。まず、給湯器のリモコンの電源をオフにします。次に、給湯器に付いている給水元栓を閉めます。これは通常、給湯器の下部や側面に取り付けられています。
その後、家中の蛇口やシャワーのお湯側を開けて、配管内の水を抜きます。キッチン、洗面所、浴室など、すべての蛇口で行うことが重要です。水が完全に出なくなるまで蛇口を開けたままにしておきます。
浴槽の水も完全に抜き、シャワーヘッドは低い位置に置いておくとよいでしょう。また、給湯器本体にある水抜き栓(機種によって位置や数は異なります)を開けて、給湯器内部の水も抜きます。
水抜き作業は給湯器の機種によって手順が異なる場合があるため、取扱説明書を参照するか、メーカーのウェブサイトで確認することをおすすめします。特に最近の高機能な給湯器では、リモコン操作で水抜きモードに切り替える機能が付いているものもあります。
水抜き作業を行った後は、再使用時に水を戻す必要があります。帰宅後や寒波が過ぎた後は、まず給湯器の水抜き栓をすべて閉め、次に給水元栓を開けます。その後、各蛇口から水が出ることを確認してから、給湯器のリモコンの電源をオンにします。
水抜き作業は少し手間がかかりますが、確実に凍結を防止できる方法です。特に寒冷地での長期不在時や、保温材やヒーターなどの対策が難しい場合には、最も信頼できる予防策となります。また、費用もかからないため、経済的な方法でもあります。
ただし、フルオート式の給湯器など、機種によっては水抜き作業が複雑なものもあります。不安がある場合は、説明書をよく読むか、専門業者に相談することをおすすめします。
給湯器の凍結が解消されてもお湯が出ないときは水道修理業者に依頼する
凍結が解消されたはずなのに、依然としてお湯が出ない、または水漏れが発生しているような場合は、配管や給湯器内部の破損が疑われます。このような症状が見られる場合は、自己判断での対処は避け、専門の水道修理業者に点検・修理を依頼することをおすすめします。
凍結による破損で多いのは、配管の接続部分やバルブの亀裂、給湯器内部の熱交換器の損傷などです。これらは素人の目では判断が難しく、適切な修理には専門知識と特殊な工具が必要となります。無理に自分で修理しようとすると、かえって状況を悪化させてしまうことがあります。
修理業者に連絡する際は、症状をできるだけ詳しく伝えることが大切です。いつから症状が現れたか、気温はどれくらいだったか、どの場所で水漏れが発生しているかなど、具体的な情報を伝えると、より適切な対応を受けられます。
業者選びのポイントとしては、地域密着型の業者や、給湯器メーカー指定の修理業者がおすすめです。特に使用している給湯器のメーカーの修理受付窓口に問い合わせると、適切な業者を紹介してもらえることが多いです。
修理費用は破損の程度や交換部品によって大きく異なりますが、一般的に軽微な配管修理で1万円前後、給湯器内部の部品交換が必要な場合は2〜5万円程度、最悪の場合、給湯器本体の交換が必要になると10万円以上かかることもあります。
また、修理を依頼する前に、住宅保険の適用が可能かを確認するとよいでしょう。多くの住宅保険では、凍結による水漏れ被害は「水災」として補償対象になっていることがあります。保険会社に連絡して、補償範囲と手続き方法を確認してみてください。
なお、賃貸住宅の場合は、まず大家さんや管理会社に連絡することが基本です。勝手に修理業者を呼ぶと、後でトラブルになる可能性があります。連絡を受けた管理会社が修理業者を手配してくれることが一般的です。
修理後は、再び凍結トラブルに見舞われないよう、前述した予防策をしっかりと講じることが重要です。特に破損した箇所は再び凍結しやすい可能性があるため、念入りな対策を取りましょう。
まとめ
給湯器の凍結は、寒冷地だけでなく、普段寒さの厳しくない地域でも急な寒波によって発生することがあります。お湯が出なくなるだけでなく、最悪の場合は配管破損による水漏れなど、深刻な被害につながる可能性もあります。
給湯器が凍結してお湯が出なくなった場合は、まず気温の上昇を待つ、給水バルブにタオルをかぶせてお湯で温める、ホットタオルやヘアドライヤーで解凍する、給湯器のリモコンをオフにして水を出すなどの方法で対処できます。ただし、無理な解凍作業は配管の破損リスクを高めるため、注意が必要です。
給湯器の凍結を防ぐためには、給水管の保温、凍結防止剤の使用、凍結予防ヒーターの活用、水抜き作業などの予防策があります。特に寒冷地や冬季に家を長期間空ける場合は、複数の対策を組み合わせることをおすすめします。
また、凍結が解消されてもお湯が出ない場合や、水漏れが発生している場合は、配管や給湯器内部の破損が考えられます。このような場合は自己判断での修理は避け、専門の修理業者に点検・修理を依頼しましょう。
冬が始まる前に給湯器の状態を確認し、必要な凍結対策を講じておくことで、寒い季節も快適にお湯を使用することができます。日頃のメンテナンスと適切な対策で、突然のお湯のトラブルを防ぎましょう。